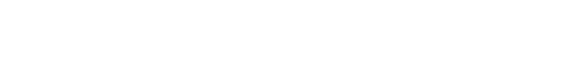ロボットの安全資格認証制度
近年、国内外の生産現場での産業用ロボットの導入が急激に進んでおり、2017年時点で、全世界での導入数は推定35万台(うち日本製ロボット約20万台)におよぶといわれています。実際に、2017年のロボット総出荷額は、前年比28.5%増(7,126億円)※ 、受注額も34.1%増(7,594億円)※と、4年連続で過去最高額となり、急激な普及がうかがい知れます。
ここでは、ロボットの安全資格認証制度について説明します。
一般社団法人日本ロボット工業会 会員ベース統計
ロボットの安全対策への新たなニーズ
産業用ロボットの急激な普及と、システムの複雑化が進む一方、ロボット起因の事故発生の割合も増加しました。
産業用ロボットの安全規格については、2015年に国内規格のJIS B 8433が改訂発効されました。しかし、今後も協働ロボットなど産業用ロボットの適用システムは多様な形態への発展していくなか、安全確保の基準と理解、実施へのニーズが高まりました。
ロボット・セーフティアセッサ資格認証制度
普及とともに増加する産業用ロボット起因の労災事故を削減するには、ロボットメーカー、システムインテグレーター、エンドユーザーが、相互業務連携に必要な知識や能力を保有するための認証基準が必要であると考えられるようになりました。そこで、2018年から、セーフティグローバル推進機構(IGSAP)と日本電気制御機器工業会(NECA)、日本認証(JC)の3団体が連携運用する「ロボット・セーフティアセッサ資格認証制度」が発足しました。
- (1)リスクアセスメントの相互業務連携
-

- (2)ロボット分野に関連する各事業従事者に要求される法規・規格の知識
-

この資格認証制度は、図(1)と(2)の知識を統合したものといえます。「セーフティアセッサ資格認証制度」による機械安全の知識を軸に、ロボット特有のリスクアセスメントやリスク低減手法などの知識を3者(ロボットメーカー・システムインテグレーター・エンドユーザー)が同等に保有し、安全確保のための業務連携をはかることを目的とした、資格認証制度です。
- 要求されるロボットの安全知識
-
- ロボットの安全規格(JIS B 8433-1, JIS B 8433-2 およびTS B 0033)
- ロボットの安全関連部の設計・構築に関する知識(製品知識を含む)
2018年7月27日に初回の資格認証試験が実施され、約3万人の資格取得者が見込まれています 。受験者は「セーフティアセッサ(SSA、SA、SLA)」資格者であることが前提となります(同時期に受験可能)。
今後も進化と多様化、システムの複雑化が示唆される産業用ロボット。その安全に関する資格は、設計製造者・システム提供者・現場の運用者(企業)の信頼性を示すものとなるといわれています。