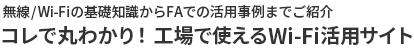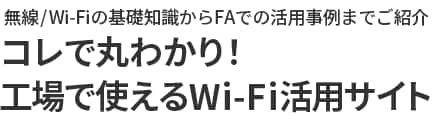Wi-Fiとそのほかの通信規格
『Wi-Fiって何?』の『LANとは』で説明していますが、無線LAN(Local Area Network:ローカルエリアネットワーク)とは、LANケーブルを使用せず、電波などの無線を使用して接続するLAN全般を指します。その通信規格のひとつがWi-Fiですが、そのほかにも5G通信やローカル5Gなど様々な通信規格があります。
こちらでは、Wi-Fiと3G/4G/5Gの違いや、『Bluetooth(ブルートゥース)』『NFC(Near Field Communication:近距離無線通信)』『ZigBee(ジグビー)』『920MHz帯無線』など、Wi-Fiのほかにも利用されている主要な無線通信規格について紹介します。
- Wi-Fiと3G/4G/5Gの関係性
- 3G/4G/5Gとは
- Wi-Fiとローカル5G
- Bluetooth(ブルートゥース)
- ZigBee(ジグビー)
- NFC(Near Field Communication:近距離無線通信)
- 920MHz帯無線
Wi-Fiと3G/4G/5Gの関係性

Wi-Fiとは、『Wi-Fiって何?』のページで説明したとおり、無線LANとして普及している通信規格のひとつです。対する3G/4G/5Gは、移動通信システムの通信規格です。スマートフォンなどで利用している通信回線となり、携帯電話の前身となる自動車電話や肩掛け式の移動電話『ショルダーフォン』で音声を電波信号で伝送するために生まれた技術です。そのため、移動していても通信が途切れにくいといった特性を持っています。
3G/4G/5Gとは
3G/4G/5Gという数字は、世代(Generation)の違いを表しています。1Gは音声通話のみのアナログ方式、2Gはメールやインターネットに対応したデジタル方式となり、それ以降の世代では通信の高速化や安定化などが進化しています。
3Gは『第3世代移動通信システム』、4Gは『第4世代移動通信システム』、5Gは『第5世代移動通信システム』の通称です。3G通信については、すべての大手キャリアがサービス終了(停波)予定を発表しており、すでに終了(停波)しているキャリアもあります。そのため現在は4G通信がメインとなり、5G通信へ移行が進められています。以下に3G/4G/5Gの最大通信速度をまとめています。
| 最大通信速度 | 最大通信速度 | |
|---|---|---|
| 3G 第3世代移動通信システム |
3G第3世代移動通信システム | 最大約384kbps |
| 4G 第4世代移動通信システム |
4G第4世代移動通信システム | 最大約1Gbps |
| 5G 第5世代移動通信システム |
5G第5世代移動通信システム | 約10Gbps~ |
Wi-Fiとローカル5G
そして近年、話題になっているのが『ローカル5G』です。ローカル5Gは、通信事業者が提供している5G通信サービスに対して、地域・企業が主体となって建物内や敷地内といった特定エリアで5Gネットワークを構築・運用・利用するものです。特定エリアで利用するという点では、Wi-Fiとローカル5Gは似ていますが、導入や運用には大きな差があります。
まず、Wi-Fiは、すでに一般家庭や企業で使われており、比較的簡単に導入できることがメリットです。導入に免許なども必要なく、数万円程度の初期費用で利用可能です。従来は、一般的な周波数帯を利用していたので、電波干渉などの問題がありましたが、6GHz帯を利用可能なWi-Fi6Eの登場により、それらの問題も解消されました。
一方のローカル5Gは、高速・大容量、低遅延、多数接続といったメリットがあります。ただし、総務省およびその地方局である総合通信局に無線局免許の申請を行い、免許交付を受ける必要があるほか、数千万円以上の初期投資が必要になり、月額費用も数十万円かかります。そのため、導入ハードルという面でローカル5Gの普及には、まだ時間がかかることが予想されます。
以下がWi-Fiとローカル5Gの違いをまとめた表になります。
| 周波数帯 | 免許 | 最大速度(理論値) | 伝送距離 | 通信の安定性 | 初期費用 | 運営費用 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローカル5G | ローカル5G | 周波数帯 | 4.6~4.9GHz帯 28.2~29.1GHz帯 |
免許 | 必要 | 最大速度(理論値) | 20Gbps | 伝送距離 | 数十m~1km | 通信の安定性 | 〇 | 初期費用 | 数千万円~ | 運営費用 | 数十万円~ | ||||||||||||
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi 6 | 周波数帯 | 2.4GHz帯 5GHz帯 |
免許 | 不要 | 不要 | 最大速度(理論値) | 9.6Gbps | 9.6Gbps | 伝送距離 | 数十m | 数十m | 通信の安定性 | △ | 初期費用 | 数十万円~ | 数十万円~ | 運営費用 | 不要 | 不要 | ||||||
| Wi-Fi 6E | 周波数帯 | 2.4GHz帯 5GHz帯 6GHz帯 |
免許 | 不要 | 最大速度(理論値) | 9.6Gbps | 伝送距離 | 数十m | 通信の安定性 | 〇 | 初期費用 | 数十万円~ | 運営費用 | 不要 | |||||||||||||
ローカル5Gは導入・運用を免許制にすることで、他の電波と干渉しにくい環境を作れる事が利点です。一方でWi-Fiは、同じ周波数帯を利用している端末が多く、電波干渉を引き起こす問題がありましたが、それもWi-Fi6Eの登場により状況が変わりました。
Wi-Fi6Eは、新しく6GHz帯が使えるようになり、電波干渉や電波混雑による遅延や速度低下という問題を解消。また、最大速度の実測値としてはローカル5Gが1Gbps前後、Wi-Fi6/Wi-Fi6Eの実測値は1Gbps程度となります。(上記表の記載数値は理論値)
たとえば、工場や生産ラインにあるPLC(Programmable Logic Controller:プログラマブルロジックコントローラー)や産業用ロボット、そのほかコンピューターとのデータ通信を無線化するのであれば、ローカル5Gではなく、Wi-Fiでも十分な機能を果たします。さらに最新のWi-Fi6Eであれば、電波干渉や電波混雑の影響も受けにくく、速度低下もしにくいので安心です。
次のページからは、具体的なWi-Fiの規格、また最新規格のWi-Fi6Eについて説明します。
Bluetooth(ブルートゥース)
スマートフォンやパソコンにマウスやキーボード、ワイヤレスイヤホンなどを接続するとき、よく利用されている無線通信規格が『Bluetooth(ブルートゥース)』です。その特徴は、1対1の通信に適しており、消費電力が少なく、映像や音楽などの比較的大容量なデータ通信に対応していることです。また、Bluetooth(ブルートゥース)は、Wi-Fiと同様に国際規格となっており、異なるメーカーの機器同士でも通信可能です。登場したのは1999年で、『Bluetooth 1.0』『Bluetooth 2.0』などバージョンごとに進化しており、2023年現在、2020年に登場した『Bluetooth 5.2』が最新版となります。10m程度の短距離での1対1の接続を基本にしていますが、最新バージョンで長距離での通信も可能になり、複数のBluetooth対応機器と接続可能なメッシュネットワークなどにも対応しています。
【特徴】
- 接続有効範囲は10m程度(規格により変動)
- 消費電力が少なく、大容量の通信にも利用可能
【主な用途】
- パソコン/スマートフォン周辺機器の接続(マウスやキーボード、イヤホンなど)
ZigBee(ジグビー)
ZigBee(ジグビー)は、2004年に標準化団体「ZigBee Alliance」によって制定された短距離無線通信規格のひとつです。IEEE 802.15.4をベースに開発され、低消費電力で通信距離は最大で30mほどになります。また、最大の特徴は、1つのネットワークに最大で6万5535端末(ネットワークの中心を構成するZigBeeを含めると6万5536端末)に接続できる点です。似た無線通信規格としてBluetoothがありますが、こちらは1対1での通信を基本にしています。それに対してZigBeeは、複数デバイスとの同時接続を得意とした短距離無線通信規格です。Bluetoothに比べ、対応製品は少ないですが、照明コントロール用の国際規格「ZigBee Light Link」が採用され、スマート電球のコントロールなどに用いられています。
【特徴】
- 接続範囲は最大で30m程度
- 消費電力が少なく、小規模の通信に利用
- 通信速度や対応機器数ではBluetoothに劣る
【主な用途】
- スマート電球のコントロールなど
NFC(Near Field Communication:近距離無線通信)
NFCは、『Near Field Communication』の略で、日本語では『近距離無線通信』と訳されます。代表的な用途は交通系電子マネーやキャッシュレス決済などで、主に機器間でのデータ交換を想定した技術です。基礎となる技術は国際標準規格ISO/IEC 18092(NFCIP-1)とISO/IEC 21481(NFCIP-2)で、13.56MHzの周波数を利用する通信距離10cm程度の近距離無線通信技術となります。その特徴は、非接触で双方向のデータ通信が可能で、比較的処理速度が速いことです。一方で通信距離が短いので通信端末を近づける必要があり、通信速度が比較的遅いため大容量のデータ通信には不向きです。NFCの規格には、『Type-A』『Type-B』『Type-F(Felica)』などがあります。またNFCは、産業用として多く利用されているRFID(Radio frequency identifier:無線周波数の識別子)に属する無線通信技術で『HF帯RFID』の一種です。
【特徴】
- 通信距離は10cm程度と短い
- 小規模の通信に利用
【主な用途】
- 交通系ICカード/RFIDタグなど
920MHz帯無線
2012年7月から日本国内で利用可能になった無線周波数帯で、主にスマートメーターリンクなどの産業用で利用されています。日本での標準規格は、一般社団法人 電波産業会(ARIB)が2012年2月に策定した「920MHz帯テレメータ用、テレコントロール用およびデータ伝送用無線設備」(STD-T108)で定められています。また、スマートメーターやHEMS機器間での無線による相互接続は、情報通信研究機構(NICT)が中心になって規格化したWi-SUNという規格があります。特徴としては、Wi-Fiで使われている2.4GHz帯に比べて障害物に強く、マルチホップ通信に対応しているので広いエリアをカバー可能で、消費電力が小さいことです。一方で、大容量のデータ通信ができないといった欠点があります。また、国ごとに使用できる周波数帯が異なるので、海外で利用する場合には注意が必要です。また、920MHz帯の電波は、UHF帯RFIDでも使用されています。
【特徴】
- 障害物に強く、長距離通信(数100m)が可能
- 消費電力が少なく、小規模の通信に利用
【主な用途】
- 電力会社のスマートメーターなど