人による省エネ
多くの企業では、すでに会社全体や工程・設備別で省エネに取り組んでいると思います。こちらでは、コストをかけず、すぐに始められる「人による省エネ」について説明します。
省エネ意識を持って行動することが大切
省エネ対策というと、「照明を水銀灯や蛍光灯からLEDタイプに交換する」「エネルギー効率の良い設備に入れ替える」などが思い浮かびますが、もっと簡単にできる方法があります。それが「人による省エネ」です。不要な照明や設備の電源を切る、照明の明るさやエアコンの温度を調整する、エア・蒸気・水などの漏れがないか点検するといった普段からの心がけでエネルギー消費を抑えることが可能です。そのために重要なことは、「従業員全員が省エネ意識を持って行動する」ことです。
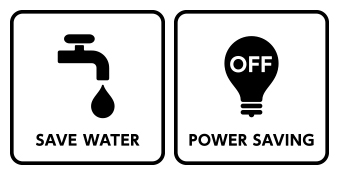
製造業で省エネを推進するには、まず省エネの意義・目標を明確にし、管理体制を整え、責任者が従業員とコミュニケーションを取ることが大切です。誰でもできる「節水・節電を心がけよう」「使わない設備の原電は切ろう」「エアコンの設定温度は〇〇にしよう」といった省エネ運動の看板設置などからはじめます。
基本はスイッチのオン・オフで過剰運用防止
「人による省エネ」の基本は、電源スイッチのこまめなオン・オフによる設備の過剰運用防止です。「不必要なものは使用をやめる・減らす」「不必要なときは使用をとめる」ことが省エネの基本です。そのためには、設備・機器の使い方を見直し、過剰運用を見つけ出し、無駄な運用をやめることが大切です。

省エネのスタートは5Sの徹底
省エネ対策のスタートは、5Sの徹底です。5Sとは、「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」の頭文字“S”を取った職場環境の維持・改善に用いられるスローガンです。すでに多くの現場で実践されている5Sは、効率的な業務を実現し、徹底することで作業効率がアップして省エネ・コスト減につながります。
例えば、5Sが不十分だと
- 整理や整頓ができていないと電源のオン・オフを見落としてしまう
- 清掃や清潔が守られていないとエア漏れや水漏れの発見が遅れる
- しつけが徹底していないと省エネ運動の教育が従業員に伝わらない
といった問題が生じます。
すぐに実践できる省エネのチェック項目
製造業の現場ですぐに実践できる省エネのポイントをまとめてみました。基本的なことばかりですが、コストもかからず取り組めるので積極的に実践してください。
照明
- 照度の見直しと照明の間引きを行う
- 不要な照明を消す
- 照明器具を定期的に掃除する
- 点灯時間を短くする など

空調
- 空調の温度設定を見直す
- 空調機器の使用台数を見直す
- 空調機器の運用時間を見直す
- 風量を見直す
- ブラインドで日射を遮蔽する
- 搬入口やバックヤードの扉を必ず閉める
- 利用していない部屋の空調をとめる
- 換気ファンの運用を見直す
- 外気導入量を見直す
- クリーンルームの循環風量を停止する
- クリーンルームの加湿を中止する
- エアコンのフィルターを清掃する
- 室内機・室外機周辺の障害物を撤去する
- 室外機周辺の温度を改善する
- 室内機の熱交換器を洗浄する
- 冷却水の温度・水量などを見直す など
冷凍・冷蔵
- 冷凍・冷蔵設備の温度設定を見直す
- 冷凍・冷蔵倉庫の時間帯別設定温度を見直す
- 冷凍・冷蔵設備の気密性を高める
- 電力ピーク時の冷凍・冷蔵庫内の負担を減らす など
給湯・衛生・オフィス機器・その他一般的な設備
- トイレ温水便座の設定を見直す
- 給湯温度を見直す
- 使わないときはOA機器のスイッチをオフにする
- パソコンのスリープモードを使う
- 退社時はパソコンの電源を落とす
- 昼間はバッテリーでノートパソコンを駆動する
- 日中は自動販売機の照明をオフにする
- 自動販売機の冷却停止時間を延長する
- 使用しないエレベーターの一部を停止する など
受変電
- 不要変圧器を遮断する など
圧縮機(コンプレッサ)
- 圧縮空気の漏れを点検する
- 空気圧縮機(コンプレッサ)の出力を見直す
- 空気圧縮機(コンプレッサ)のフィルターを清掃する
- 空気圧縮機(コンプレッサ)の吸気温度を低く抑える など
廃水処理
- 暖気層のブロワを間欠運転にする
- 排水処理施設の稼働を夜間にシフトする など
生産
- ライン停止時や非操業時は設備の電源をオフにする
- 集塵装置のファン動力を抑える
- 定期的に設備に給油して機械的なエネルギー損失を減らす
- 駆動ベルト・チェーンの適切に保つ
- 製品・設備の過剰な冷却を見直す
- 冷却水の漏れ・圧力・温度などを定期的に点検する
- 加熱装置の設定温度を見直す
- 熱処理などで工業炉内の温度制御を見直す
- 輸送用コンベアの運転を見直す
- 生産開始時間を見直す
- 生産装置のアイドル運転の時間を短縮する など
省エネ効率の良い機器・材料・プラン選び
こちらのページでは、「人による省エネ」としてコストのかからない手軽な省エネ対策を紹介しました。しかし、本格的に省エネ対策を行う場合は、設備の入れ替えなど初期費用が発生します。省エネ対策では、長期的なコストを考慮して機器・材料・プラン選びをすることが大切です。次のページからは、「一般工場内設備」「液体・生産設備」「熱処理設備」「給排水・衛生設備」に分けて省エネ対策例を説明します。また、省エネでは、どの設備でどれだけのエネルギーが利用されてているのかを知るために「エネルギーの見える化」がカギとなります。そこでIoT活用術も併せて説明します。





